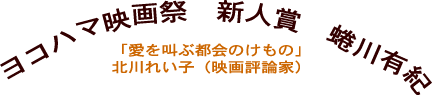
|
「狂った果実」の蜷川有紀を観てすぐに頭に浮かんだのは、異色SF作家ハーラン・エリスンの短編「世界の中心で愛を叫んだけもの」に登場する男の話であった。 狂気と暴力の神話を描くこの小説のテーマ・エピソードとして冒頭に語られるその男は、盗んだ猛毒を各家庭の裏口に配達された牛乳びんの中に入れ歩き、二百人の老若男女を絶命させる。そして時限爆弾を仕かけたスーツケースを母に持たせて旅客機に乗せ、乗客もろとも爆死させ、火だるまとなった旅客機は、運悪く公共水泳プールに落下し、さらに多くの犠牲者がでる。そのあと男は、超満員の喚声をあげているスタジアムに行き、サブ・マシンガンを射ちまくる。 裁判に掛けられた男は、だが、ガス室での死刑を宣告される直前、顔をふしぎな至福の表情に輝かせ、叫ぶのだ。「おれは世界のみんなを愛してる。ほんとうだ、神様に誓ってもいい。おれは、みんなを愛してる。おまえたちみんなを!」 もちろんこの男の無差別大量殺人だけをみれば、現実にも似たような話は世界中にころがっているし、長編記録映画「アメリカン・バイオレンス」など、狂気と暴力による無差別殺人のオンパレードで、観ている最中に、いつこっちも殺られるか、金輪際アメリカへなんかいくものかと、まったく生きた心地もなかったのだが、「世界の中心で愛を叫んだけもの」における狂気と暴力のエピソードの男は、このあと、異空間の断罪人たちによって告発、浄化され、やがて全宇宙的破滅が用意される。 そしてハーラン・エリスンは、けものの消滅に反対する科学者にこう言わせる。「狂気は生きた蒸気だ。力だ。」だがこの科学者も人類に対する反逆者として浄化されてしまう。 つまりここに書かれた愛のパラドックスと人間の暴力的本能は、そっくりそのまま「狂った果実」の蜷川有紀の存在と重なるのだ。 彼女は、まるで愛に植えた小さなけものように本間優二につきまとい、青年の無関心を暴力でねじまげてまで、ひっかきまわす。なざなら、愛しているから、愛されたいから、関わりたいから、受けとめたいから。 '81年に登場した軽い青春映画の、シロっぽいヒロインたちは、みなユーレイのように透明で無関心をきどり、季節の衣装並に男をとっかえひっかえするだけだったが、蜷川有紀が演じた金持ち娘は、昼はガソリン・スタンド、夜は暴力バーで働く地方出の青年に命の熱い蒸気をあびせかけ、都会の孤独と残酷さの女神となり、青年の中にかくされた暴力本能に火をつけるのだ。 めったに笑わない蜷川有紀の表情は、その確質な演技とあいまって、愛の残酷なゲームをリードし、'81年、もっとも攻撃的なヒロインとして、作品共ども、ベスト・ワンである。 若者たちのいやがらせがエスカレートする暴力バーのシーンの、彼女の手さぐりのゴーマンさも良かった。 |